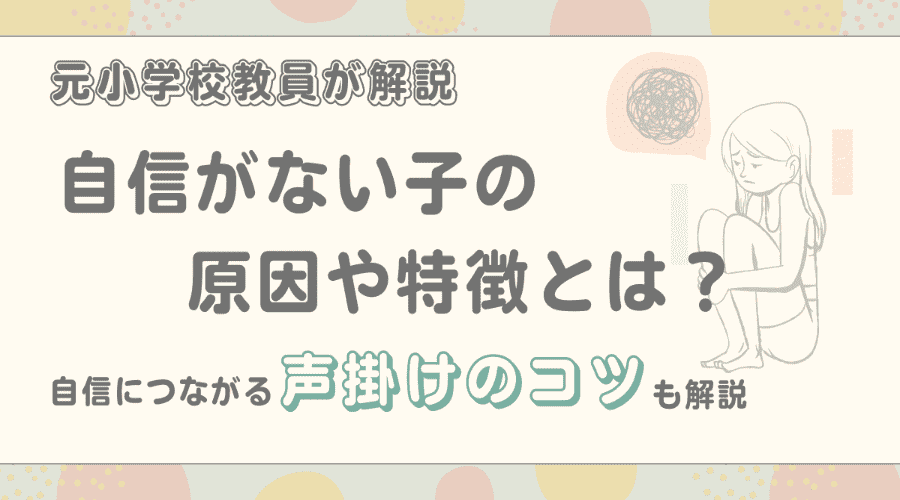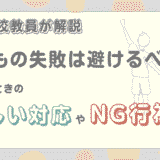「新しいことに取り組ませようとしても、自信がなく積極的にやろうとしない」
「子どもに自信をつけるために親ができることはあるのかな」
なかなか自信を持てず、新しいことに挑戦できない子どもを見ると「このままで大丈夫かな……」と不安になってしまいますよね。
結論、子どもが自分に自信を持てないのは、以下4つの原因があると考えられます。
上記以外にも、親の何気ない発言によって子どもが自信を失ってしまうケースもあります。
子どもが自信を持てないままでいると、チャレンジを恐れて成長の機会を逃し、さまざまな場面で本来の実力を発揮できなくなるかもしれません。
子どもに自信をつけるには「自分ならできる」「失敗しても大丈夫」と思えるよう、日々の関わりを工夫することが大切です。
そこで本記事では、子どもが自信を持てなくなる原因や特徴、親のNG行動や自信を持たせる方法を解説します。
記事内で紹介している方法を実践すれば、子どもに自信を持たせつつ、良好な親子関係を築けるでしょう。
子どもの自信を高めて健やかな成長につなげたい方は、ぜひ参考にしてください。
子どもが自信を持てなくなる4つの原因

子どもが自信を持てなくなる原因として考えられるのは、以下の4つです。
過去の経験から「頑張りを認めてもらえない」と感じている子は、新たな挑戦を過剰に恐れてしまう傾向があります。
子どもに自信をつけるヒントを得るためにも、一つずつ原因を探っていきましょう。
1.褒められた経験があまりない
小さい頃から周りの大人に褒められる経験があまりなかった子どもは、自分に自信を持てなくなってしまいます。
子どもに限らず大人も、自分の頑張りを誰かに認めてもらえるのは嬉しいですよね。
子どもは特に、自分の努力を親や先生に褒めてもらうことで「もっと頑張ろう」と前向きな気持ちになれます。
しかし、どれだけ努力しても褒められない環境にいると、子どもは「頑張っても意味がない」と挑戦する意欲を失ってしまうのです。
褒められるよりもダメ出しされる機会が増えれば、大人の顔色をうかがって行動するようになるかもしれません。
子どもに自信を持たせるためには、完璧にできていなくても成長した部分に注目し、前向きな言葉をかけるようにしましょう。
2.日常的に叱られる場面が多い
家庭や学校などで日常的に叱られる場面が多いことも、子どもの自信を失わせてしまう原因の一つです。
何度も叱られるうちに「自分はダメな子だ」と考え、何事にも積極的に挑戦できなくなってしまいます。
子どもが危険なことをしていたり、ルールを守らなかったりしたとき、厳しく叱るのは親として当然のことです。
しかし、以下のような言葉を日常的にかけていると、子どもは自分自身を否定するようになるかもしれません。
- また部屋を片付けていない!早く片付けなきゃダメでしょ
- いつになったらできるようになるの!
- 何度同じことを言ったらわかるの!
子どもを叱るときは、人格を否定する言葉は避けつつ、何がいけなかったのかを簡潔に伝えるのがポイントです。
ダメなことはダメだと伝え、努力や頑張りが見られたときは積極的に褒めることで、子どもの成長にもつながるでしょう。
3.過去に失敗して怒られた経験を忘れられない
過去に失敗して怒られた経験を忘れられず、新たな物事に挑戦する自信を失っているケースもあります。
挑戦する意欲よりも「また怒られるかも」「失敗したらどうしよう」という不安が大きくなり、行動を起こせなくなってしまうのです。
失敗経験がトラウマとして残り続けると、大人になってもネガティブ思考から抜け出せないかもしれません。
過去の経験が原因で自信を失っている場合は、小さな成功体験を積み重ね、少しずつトラウマを克服することが大切です。
達成感を味わう機会を増やすことで「やればできる」と思えるようになると、徐々に失敗を恐れず行動できるようになるでしょう。
4.親子のコミュニケーションが足りない
親子のコミュニケーション不足が、子どもの自信喪失につながっている可能性もあります。
これまで紹介した原因がピンとこない方は、子どもと十分なコミュニケーションを取れているか、一度振り返ってみましょう。
子どもがいる家庭の多くは、以下の理由で親子のコミュニケーションが不足しがちです。
- 共働きで家に帰ってくる時間が遅い
- 子どもが習い事を夜遅くまでやっている
- 下の子が産まれたばかりで育児に追われている
スマホやテレビに集中してしまい、子どもと会話する時間が減っているケースも少なくありません。
親に話を聞いてもらえなかったり構ってもらえなかったりすると、子どもは「自分に興味を持ってくれない」と自信をなくしてしまいます。
親子のコミュニケーションを通して自信を持たせるには、たとえ短時間でも、子どもと向き合う機会を意識的につくりましょう。
子どもの自信を失わせてしまう親のNG行動

周囲の環境や過去の経験だけでなく、親の何気ない発言や行動で子どもの自信を失わせる場合もあります。
誰でも無意識にやってしまいがちな行動もあるので、ぜひチェックしてみてください。
上記に当てはまるからといって、自分を責める必要はありません。子どもと良好な関係を築くためにも、改善点を見つけて関わり方を工夫していきましょう。
思い込み・決めつけで発言してしまう
「これが苦手なはず」という思い込みや、「これくらいできて当たり前」という決めつけによる発言は、子どもが自信を失う原因となってしまいます。
成長のチャンスが巡ってきても、親に言われることで「自分には無理だ」と思い込んでしまい、前向きに取り組めなくなるかもしれません。
子どもの自信を奪ってしまう思い込み・決めつけの発言は、以下のとおりです。普段の何気ない会話で口にしていないか、チェックしてみてください。
- 運動は苦手なんだから無理しなくてもいいよ
- また失敗するんじゃないの?
- ◯歳にもなって、こんなこともできないの?
- そんなの言わなくてもわかるでしょ
子どもが新しい物事に挑戦するときは、思い込みや決めつけで可能性を否定するのではなく、向上心を刺激して成長の手助けをしてあげましょう。
きょうだいや周りの友達と比較する
子どもを叱るときにやりがちな、きょうだいや周りの友達と比較する発言にも注意が必要です。
周りと比較されることで、子どもは「自分はダメな子だ」「全部自分が悪いんだ」と思い込み、自信をなくしてしまいます。
厳しく叱っているわけでなくても、以下の発言はできる限り避けましょう。
- お兄ちゃんはもっとしっかりしてたのに……
- ◯◯(妹や弟)は宿題をしているのに、どうしてあなたはやらないの?
- △△くんはいつもテストで100点を取っているみたいだよ
- ◯◯ちゃんはきちんと挨拶ができて、えらいね
子どもの成長を促す際は周りと比較するのではなく、本人の行動に焦点を当てて、課題に気づかせたり褒めたりすることが大切です。
「自分を見てくれている」と実感できると、子どもの自己肯定感は高まり、少しずつ自信もつけられますよ。
子どものやることを細かく指示している
勉強などで子どもが上手に取り組めない様子を見ると、親としては「助けてあげたい」という気持ちから、つい口を出したくなりますよね。
ただ、心配するあまり子どものやることを細かく指示すると、自分で考え行動する力が育たなくなってしまいます。
一人で何かに取り組もうと思っても、どうすれば良いのかわからないため、自信を失って何事にも消極的になるでしょう。

「失敗させたくない」という気持ちもわかりますが、子どもが困難を乗り越えて成長するためには、失敗から学ぶ経験も必要です!
子どもに自信を持たせるには、結果だけでなくプロセスも重視し、最後まで信じて見守ることを意識しましょう。
励ましの言葉がプレッシャーになっている可能性もある
子どもに対する励ましの言葉も、自信を失わせる原因となる場合があります。
以下の発言に隠された無意識の「ダメ出し」によって、子どもは大きなプレッシャーを感じてしまうのです。
- テスト頑張ったね!もう少し頑張れば100点だよ
- この部分を綺麗に片付ければ完璧だね
- 次の大会ではもっと高い順位を取れそうだね
上記の場合「もう少し頑張れば」「もっと高い順位」という部分から、子どもは「完璧を目指さなければ」とプレッシャーを感じる可能性があります。
これまでの努力を否定された気持ちになり、自己嫌悪に陥るかもしれません。
子どもを励ますときは、今の頑張りを最大限受け止めてから、次にどうしたいかを一緒に考えるのがポイントです。
自分の頑張りを肯定的に受け止めてもらうことで、自然と自信もつき、失敗しても諦めず挑戦できるようになりますよ。
自分に自信がない子の特徴

失敗の経験や、親からの否定的な言葉によって自信を失っている子どもには、以下の特徴が見られる傾向にあります。
- 周りにどう思われるのかを気にする
- 完璧にできない自分を責めてしまう
- 他者と比較して自己嫌悪に陥る
- 失敗を恐れて積極的に挑戦できない
- 成功しても素直に喜べない
基本的に自信がない子は、自分を過剰に低く評価したり、ちょっとしたことで自分を責めたりしてしまいがちです。
成功体験があっても素直に喜べず、周りの人から「全然嬉しそうじゃない」と思われることもあります。周りの目を気にして自分の意見を押し殺してしまうのも、自信がない子の特徴です。
子どもに上記の特徴が見られる場合は、次から紹介する方法で少しずつ安心感を与え、自信や主体性をつけていきましょう。
声掛けのコツも紹介!子どもに自信を持たせる方法

子どもの自信は、短期間で簡単につくものではありません。
以下の対応を粘り強く行い、時間をかけて少しずつ自信を持たせましょう。
上記をヒントに子どもとの関わりを見直し、できることから改善してみてください。
できない部分も含めてありのままを受け入れる
子どもを褒めることは重要ですが、長所ばかりに目を向けると「良い子でいなければ」とプレッシャーを感じる可能性があります。
子どもに自信を持たせるには、長所だけでなく短所も含めて、ありのままを受け入れる姿勢を示しましょう。
子どもが失敗したときや困難に直面したときは特に、以下のような声掛けを意識してみてください。
- 失敗しても、あなたが大事なことは変わらないから大丈夫
- たとえ上手くいかなくても私達はずっと味方だからね
- そのままのあなたが私達にとって大切な存在なんだよ
「どんな自分でも好きでいてくれる」という実感を持てると、失敗を恐れず挑戦できるようになり、成長にもつながるはずです。

口にするのは恥ずかしいと感じる方もいるかもしれませんが、お互い嬉しい気持ちになれるので、ぜひ使ってみてくださいね。
日々のスキンシップや会話を大切にする
子どもに自信を持たせるには、日々のスキンシップや会話を意識的に増やすのも効果的です。
「自分に興味を持ってくれている」「大事にされている」と安心感が高まり、自信を持って行動できるようになります。
子どもが幼児・低学年の場合は、以下のスキンシップを試してみるのがおすすめです。
- 挨拶のタッチやハグをする
- 寝る前に頭を撫でる
- 手をつないで寝る
仕事や家事で忙しい方でも、挨拶など毎日の習慣にプラスして触れ合う瞬間をつくると、子どもの安心感を高められます。
高学年から上の年齢になると、スキンシップを嫌がる可能性があるため、以下のポイントを意識して会話を充実させましょう。
- スマホや家事の手を止めて子どもを見る
- 子どもの話をさえぎらず最後まで聞く
- 言葉の背景にある気持ちを汲み取って共感する
子どもの話を真剣に聞いていることが伝わると、会話の時間が短くても「自分と向き合ってくれている」と満足感を持てるはずです。
ただし、無理にコミュニケーションを取ろうとすると、子どもの反発を招く可能性があります。あくまでも子どもの意思を尊重しつつ、お互い無理のない距離感でコミュニケーションを取りましょう。
小さな成功体験を積み重ねる
子どもが自信を持って行動するためには、好きな遊びや勉強などで、小さな成功体験を積み重ねる方法も取り入れてみてください。
「できた」「わかった」という経験を積むことで自信がつき、新たな活動に対しても失敗を恐れず取り組めるようになります。
日常生活で簡単に取り組める成功体験の例は、以下のとおりです。
- 簡単な手品や工作などを家族に披露する
- 「漢字を5個覚える」など1日の学習目標を設定する
- 好きな教科で少し難易度が高い問題に挑戦してみる
- 短時間で終わるお手伝いを頼む
このとき「上手にできたね!」「すごく助かったよ」とポジティブな言葉をかけると、さらに自信を高められるでしょう。
結果だけでなく成長の過程にも目を向ける
子どもの努力を結果だけで評価すると、どれだけ頑張っても否定されている気持ちになり、自信を失ってしまいます。
そのため、子どもに自信を持たせるには結果だけでなく成長の過程にも目を向け、以下のような声掛けをしましょう。
- こんなに上手になったのは、毎日コツコツ練習していたからだね
- 試合に負けそうでも最後まで諦めずに戦ったのが格好良かったよ
- 毎週お手伝いをしてくれて、本当に助かっているよ
- 自分なりに工夫して勉強したんだね!すごく良いと思うよ
良い結果が出なかったとしても、成長の過程を褒めてもらえると、子どもは「もっと頑張ろう」と前向きに挑戦できるようになります。
ただし、やみくもに褒めようとして中身のない言葉を伝えるのは逆効果です。子どもの様子をじっくりと観察して褒めるポイントを見つけ、心を込めて温かい言葉をかけましょう。
自信がない子への対応で意識すべき2つのポイント

なかなか自信が持てない子どもに適切な対応を行うためには、以下2つのポイントを意識することが大切です。
親自身が心に余裕を持って子どもと向き合い、ありのままを受け入れることができると、自然と肯定的に関われるようになります。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
1.自信をつけることにこだわりすぎない
「子どもに自信をつけさせなければ」という強いこだわりは、できる限りなくしましょう。過剰な期待が子どもにとって重圧となり、かえって自信を持てなくなる可能性があります。
たしかに、子どもが自信を持つことは新しいチャレンジをしたり、困難を乗り越えたりするうえで大事なステップです。
しかし、親が自信をつけることにこだわりすぎてしまうと、子どもは「今の自分」を認めてもらえない気持ちになり、頑張る気力を失ってしまいます。
子どもを安心させるには、自信を持てない部分も含め、すべて「あなたはあなた」と受け入れることが大切です。
子どもに自信がない様子が見られても、まずは「それでもあなたは大切な存在だよ」と伝えることを意識しましょう。
2.親自身が一人で悩みを抱え込まない
親自身が子育てに自信を持てず、悩みを抱えていると、不安やストレスから否定的な発言・行動が増えやすくなります。
そのため、子どもに自信を持たせるには、親自身が子育ての悩みを一人で抱え込まない工夫を取り入れることも大切です。
以下を参考に「これならできそう」と思える方法を試してみてください。
- 1日1回でも自分をねぎらう言葉をかける
- 短時間でも趣味を楽しむ「自分の時間」をつくる
- 家族や友人など信頼できる人と話す機会を増やす
- 子育て専用の相談窓口を利用する
「今日も頑張ったね」「よくやってるよ」など、自分をねぎらう言葉をかけると、自己否定に陥る考え方を止めることができます。
たとえ5分でも、好きな音楽を聴いたり本を読んだりする時間を持つことで「明日からまた頑張ろう」と思えるかもしれません。
家族や友人などに話せない悩みがある場合は、子育て専用の相談窓口を利用するのも一つの手です。以下のページから、気になる相談窓口をチェックしてみてください。
参考:相談窓口|こども家庭庁
気持ちに余裕のある対応で少しずつ子どもに自信をつけよう

本記事では、子どもが自信を持てなくなる原因や特徴、親のNG行動や自信を持たせる方法を解説しました。
子どもが自信を持てなくなる原因には、以下の4つが挙げられます。
親の何気ない発言や行動で子どもの自信を失わせてしまう場合もあるため、注意しなければなりません。
子どもに自信を持たせるためには、以下の方法を実践しましょう。
自信を持たせることにこだわりすぎず、親自身の不安や悩みを解消することで、気持ちに余裕のある対応ができるようになります。
本記事を参考に、ポジティブな関わりを意識して少しずつ子どもの自信を高めてくださいね。